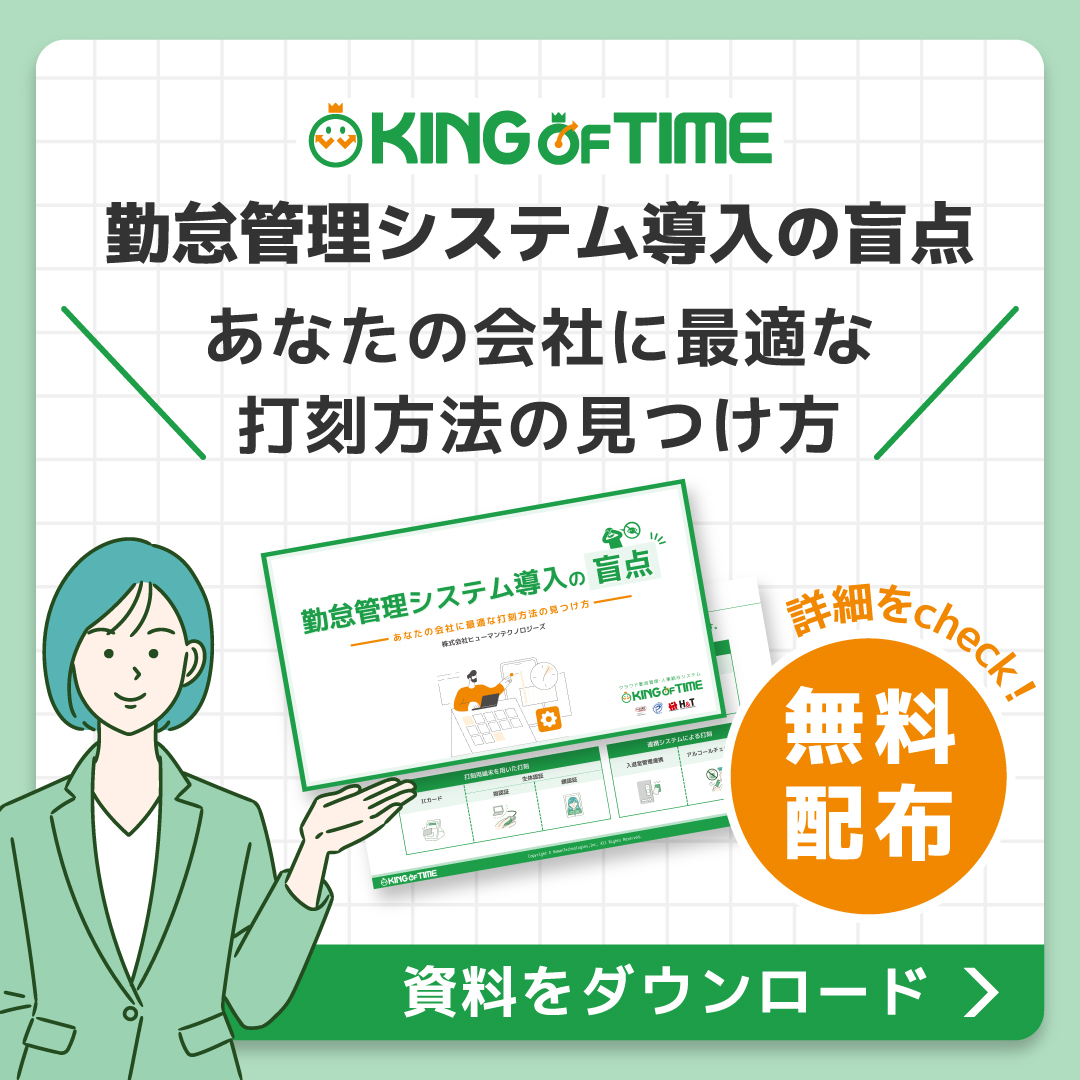ジョブディスクリプションとは、職務内容・責任範囲・必要なスキルなどを明確に言語化した職務記述書です。ジョブ型雇用への注目が高まる中、組織の生産性向上や人材育成、採用のミスマッチ防止など多くのメリットが期待されています。
本記事では、ジョブディスクリプションの概要から記載例までわかりやすく解説します。
目次
ジョブディスクリプションとは

ジョブディスクリプションとは、職務の内容や範囲、責任、求められるスキルなどを詳細に記した「職務の定義書」のことです。採用や人事評価において基準を明確にする役割を担い、業務分担の曖昧さや属人的な働き方の回避にもつながります。
もともとは欧米で広く浸透している仕組みですが、近年は日本でも職務ベースのマネジメントを志向する企業が増えていて、ジョブディスクリプションの導入が注目されています。組織にとって透明性や生産性の向上が見込める取り組みと言えるでしょう。
ジョブディスクリプションが注目される背景

近年、働き方の多様化や雇用制度の変化により、ジョブディスクリプションの重要性が高まっています。それにより、企業が求める人材像や役割を明確にする動きが広がりつつあります。
ジョブ型雇用への関心が高まっている
従来の日本では人を先に採用し、その後に業務を割り当てるメンバーシップ型雇用が主流でした。しかし近年では、職務に適した人材を採用・評価するジョブ型雇用への関心が急速に高まっています。この流れを支える土台として、ジョブディスクリプションが注目されているのです。
職務内容や責任範囲を明文化することで、成果主義や同一労働同一賃金にも対応しやすくなります。既に大手企業を中心に導入が進んでいます。
関連記事:ジョブ型雇用とは?注目の背景・導入手順・メリット・デメリットを解説
専門職・外国人材の採用ニーズの拡大も影響している
ITエンジニアを始めとする専門人材の不足や、外国人労働者の増加もジョブ型雇用を後押しする要因となっています。
こうした人材は、自身の役割や期待される成果が明確に示されている職場環境を好む傾向があり、ジョブディスクリプションの整備は採用や定着にも大きく影響します。
文化的・言語的なギャップがある場合でも、職務を文書化することにより誤解を避け、共通理解を促進できる点もメリット。グローバルな人材戦略においても、職務の明文化は欠かせない取り組みと言えるでしょう。
ジョブディスクリプション導入のメリット

ジョブディスクリプションの導入は、単なる業務の可視化にとどまらず、組織運営や人材戦略において多くのメリットをもたらします。ここではジョブディスクリプションの導入によって得られるメリットを紹介します。
組織の生産性を底上げする仕組みづくりができる
ジョブディスクリプションは、業務の目的や範囲、責任の所在を明確にすることによって、組織全体の生産性を底上げする仕組みを築けます。役割が可視化されることで、業務の重複やあいまいな押し付け合いが減少し、各人が自らの職務に集中しやすくなります。
さらに、必要なスキルを持つ人材を適切なポジションに配置できるため、育成にかかるコストを抑えながら高い成果を実現できる体制づくりも可能です。
評価と報酬の納得感を生む基盤になる
ジョブディスクリプションは、職務の内容と成果基準を事前に明文化することで、人事評価の公平性を支える土台となります。業務の目的やゴールが定義されていれば、評価時に成果との差を客観的に把握でき、評価者が異なっても判断のブレが生じにくくなります。
また、職務と報酬を連動させる制度とも相性が良く、「どの業務にいくらの報酬が支払われるのか」が明確になれば、従業員にとっての納得感やモチベーションも高まりやすいでしょう。
採用要件が明確になり、ミスマッチを防げる
ジョブディスクリプションを整備することで、採用において「どのような人材を求めているのか」を明確にできます。職務内容や必要なスキル・経験があらかじめ文書化されていれば、求職者との認識のズレが起こりにくく、入社後の早期離職リスクも軽減されるはずです。
加えて、採用基準を関係者間で共有しておけば、面接官ごとの判断のバラつきも減り、組織として一貫性のある人材選考が可能になります。
スペシャリスト人材の育成にもつながる
職務に必要なスキルや求められる成果が明確になることで、従業員は自身が強化すべき能力を把握しやすくなります。ジョブディスクリプションをもとにキャリアパスや目標を設計すれば、戦略的な人材育成が可能になるはずです。
特に専門性を深めたい人材にとっては、自らの成長を自律的に後押しできる、頼もしい指針となるでしょう。
ジョブディスクリプション導入のデメリット
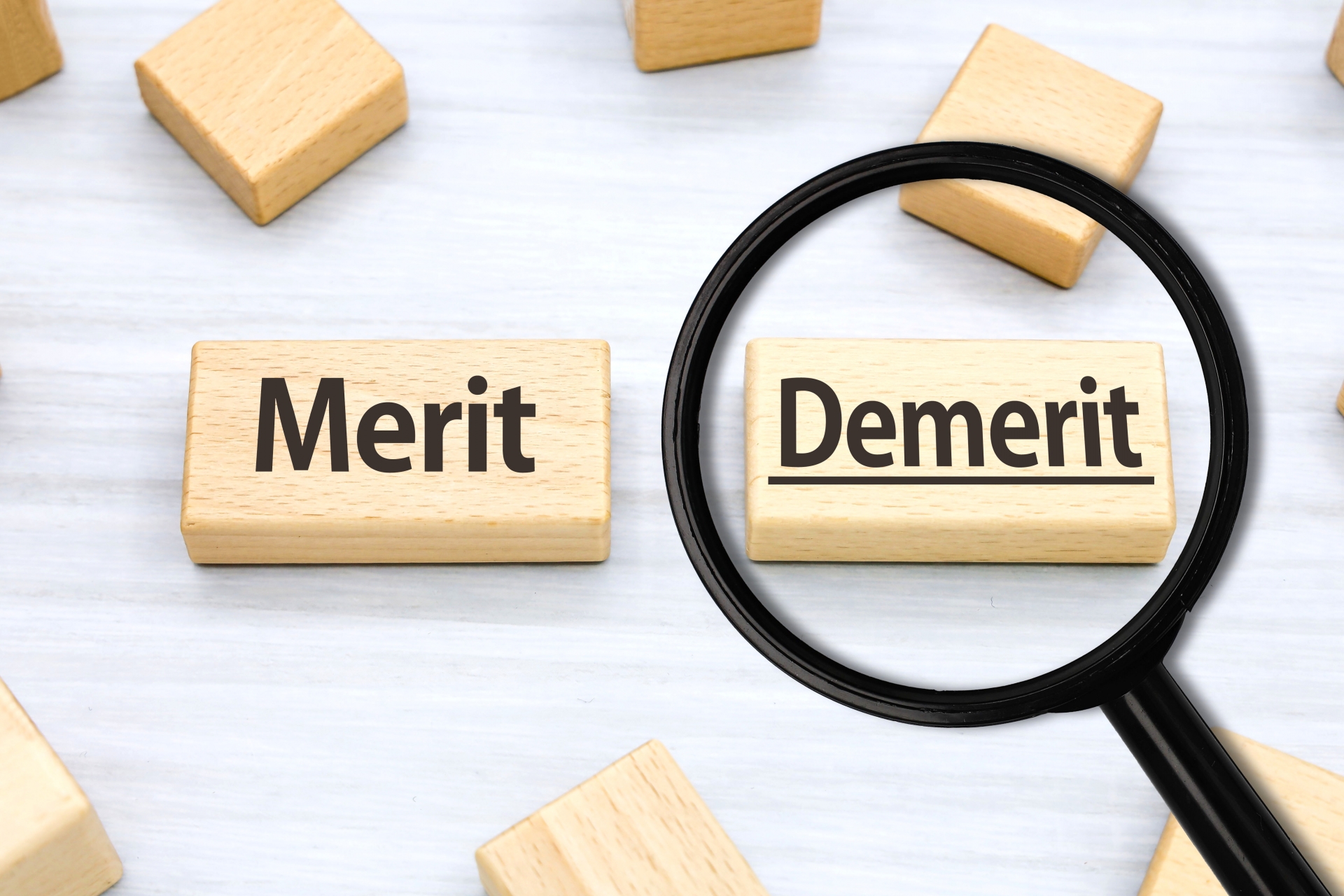
ジョブディスクリプションには多くのメリットがありますが、導入・運用には注意すべきポイントもあります。ここではデメリットを紹介します。
仕事の柔軟性が失われるリスクがある
ジョブディスクリプションは職務を明確に定義するため、役割の境界が固定化されやすくなります。その結果、「これは自分の仕事ではない」といった姿勢が生まれ、周囲との連携や助け合いが損なわれる可能性も。
特に変化の激しい業務環境や少人数の組織では、各人が柔軟に動ける体制が必要不可欠です。ジョブディスクリプションにとらわれすぎず、柔軟な対応力を保てる仕組みづくりが求められるでしょう。
ゼネラリスト育成や異動のしにくさがある
職務が明文化されることで、異動やジョブローテーションなど社内での柔軟な人材配置が難しくなる場合があります。特に、「幅広い経験を通じて将来の経営人材を育成する」という日本企業の人事戦略とは相性が合わない面もあるでしょう。
導入に際しては、ジョブディスクリプションと人材戦略の方向性を丁寧にすり合わせる必要があります。
作成・運用に手間がかかる
ジョブディスクリプションの導入では、作成と運用の両面で一定の工数が発生します。各職務の業務内容を丁寧に洗い出し、関係部門と調整を重ねて文書化する作業には、時間と労力がかかります。
また、作成後も変化に応じた定期的な見直しと管理体制が欠かせません。形骸化を防ぐためにも、社内の理解と協力を得ながら運用していくことが重要です。
ジョブディスクリプションの導入と運用を成功させるためのポイント

ジョブディスクリプションを効果的に活用するには、導入後の運用体制や組織全体での取り組みが欠かせません。ここでは、成功のための実践ポイントを解説します。
全体最適を見据え、現場と経営の両視点で職務を捉える
ジョブディスクリプションを形だけで終わらせないためには、個々の職務だけを見るのではなく、周辺業務や他部署との関係も含めて広い視野で設計することが重要です。
定義が曖昧すぎれば役割がぼやけ、逆に細かく決めすぎると現場での柔軟性を奪う結果になりかねません。現場への丁寧なヒアリングを通じて実情を捉えつつ、経営や人事の戦略的な観点を加えると良いでしょう。
多様な立場の視点を反映させることで納得感が生まれ、現場からの抵抗や形骸化のリスクも抑えられるはずです。
一度作って終わりではなく定期的に見直す
ジョブディスクリプションは、変化に対応しながら運用してこそ価値があります。組織の目指す方向性や人員体制、業務内容が変われば、それに応じて職務の定義も見直す必要があるでしょう。
年に一度、または半期ごとの定期点検を行い、実際の業務内容と文書の内容にズレが生じていないか確認したいところです。もし内容が実態とかけ離れていれば、評価制度や業務の分担にも悪影響を及ぼしかねません。
継続的な見直しを前提とした運用が、制度の有効性を保つポイントです。
勤怠管理などのSaaSを活用して運用負荷を減らす
ジョブディスクリプションの維持・運用には、どうしても一定の工数が発生します。勤怠管理SaaS製品に下記のシステムを組み合わせることで、業務効率化や業務ごとの稼働時間の可視化を、より効果的に実現できます。
・勤怠データを分析できるシステム(例:KING OF TIME データ分析)
・工数・タスク管理システム(BacklogやAsanaなど)
例えば、業務ごとの稼働時間を可視化できれば、ジョブディスクリプションと実務のギャップが浮き彫りになり、見直しも可能です。人事・労務の情報がデジタルで一元化されていれば、職務の棚卸しや内容のアップデートもスムーズになるでしょう。
ジョブディスクリプションの作り方

ジョブディスクリプションは、正確かつ実務に即した内容であることが重要です。ここでは、作成の基本ステップをわかりやすく解説します。
1.職務の現状把握とヒアリングをする
まずは、対象となる職務の実態を把握することからスタートします。業務内容はもちろん、責任範囲・権限・必要なスキルや資格など、幅広い情報が必要です。
机上で整理するだけでは実態とのズレが生じやすいため、現場の担当者や管理職へのヒアリングは欠かせません。複数人の声を拾い上げることで視点の偏りを防ぎ、職務の全体像が見えてきます。
2.情報を精査・整理する
集めた情報はそのまま使うのではなく、要点を絞って整理しましょう。特に、「何を、なぜ、どのように行うのか」といった視点で業務を細かく分解していく作業が重要です。あわせて、業務の重要度や頻度、優先度などで分類すると、内容の重みづけが可能になります。
実務からかけ離れた記述にならないよう、必要に応じて管理者や専門家の意見も取り入れてください。
3.実務に落とし込む形で文書化する
整理した内容をもとに、ジョブディスクリプションを文書化します。基本的にはA4一枚程度に収まるボリュームで、「職務の目的」「責任範囲」「業務内容」「必要スキル」などを明示しましょう。
完成後には、実際に関わる担当者やマネージャー、必要に応じて経営層にも確認を取り、内容の妥当性をチェックすることが欠かせません。業務は常に変化するものなので、将来的な変更の可能性を記載しておくと、柔軟な運用にもつながるでしょう。
ジョブディスクリプションへの記載例

ジョブディスクリプションを作成する際は、業務内容の記載にとどまらず、組織内での位置づけや雇用条件、求められるスキルなど、多角的な情報を網羅する必要があります。一般的な項目の記載例は次のとおりです。
・職種、職務名、職務等級
・所属、上司、部下
・会社概要
・職務概要、期待されるミッション、業務目標、具体的な職務内容
・資格、経験、スキル、知識
・雇用形態、勤務時間、休日、勤務地、報酬
・福利厚生
採用や人事評価、育成など、目的に応じて記載内容を取捨選択し、業種や企業文化に合わせてカスタマイズを行いましょう。
ジョブディスクリプションは人と組織の可能性を引き出す土台

ジョブディスクリプションは、業務の可視化や役割の明確化を通じて、個人の力を最大限に引き出し、組織全体の生産性を高める重要な土台です。制度として導入するだけではなく、運用・改善を繰り返すことで、変化に強い組織づくりにつながります。
自社の状況に合わせて運用の負担を減らせるツールを活用しつつ、生産性の向上につなげましょう。