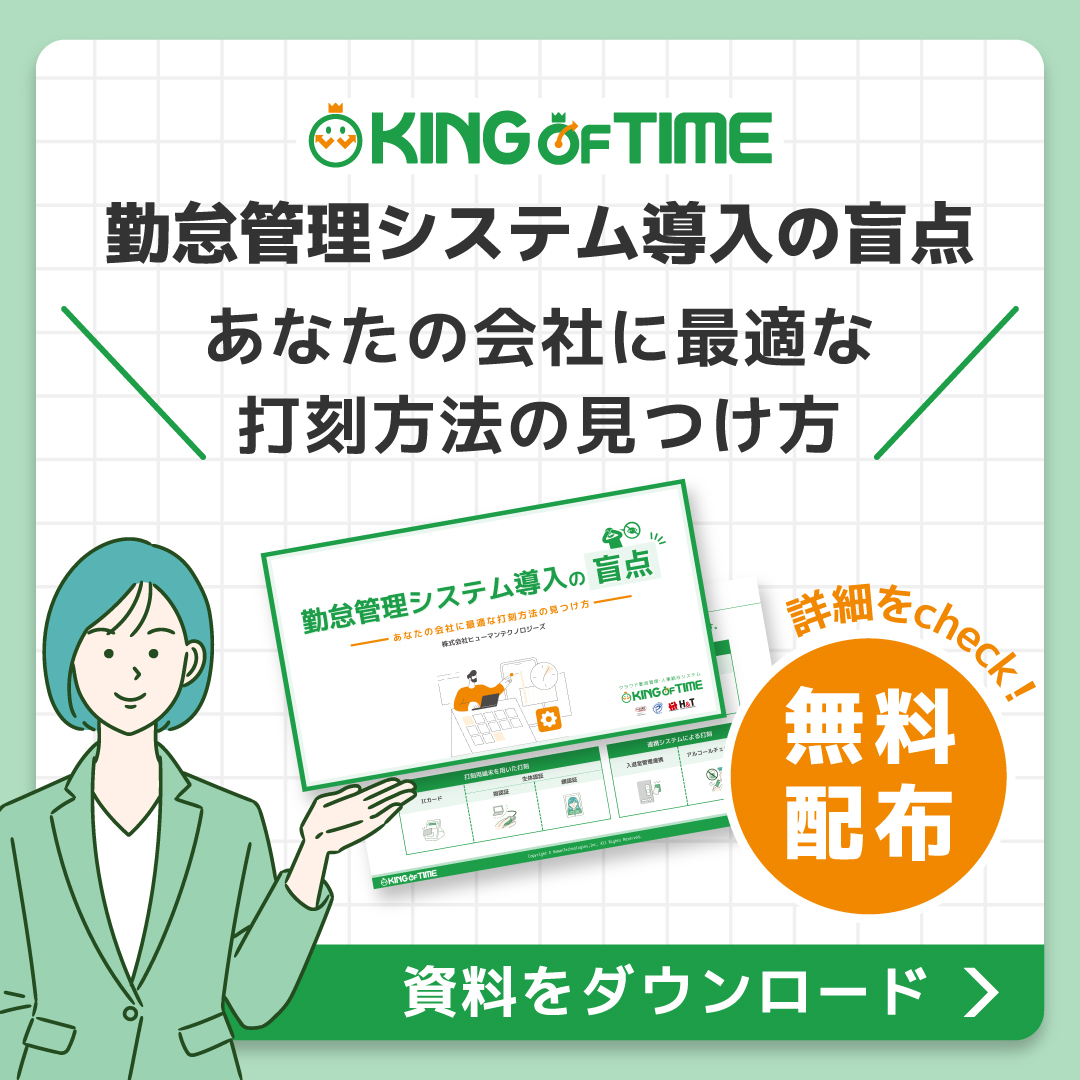人時生産性とは、従業員1人が1時間あたりにどれだけの利益(粗利)を生み出しているかを示す指標です。人材不足や働き方改革が進む今、企業のパフォーマンスを客観的に把握するための重要な経営指標として注目されています。
この記事では、人時生産性の概要や計算方法、向上を妨げる原因や改善するためのポイントをわかりやすく解説します。
目次
人時生産性(にんじせいさんせい)とは

企業の業績を高めるには、限られた人員や時間の中でどれだけ効率的に利益を出せているかを把握することが重要です。
人時生産性はその指標として活用され、業務効率の改善や人材配置の見直しなど、現場と経営の両面で実践的に役立ちます。
従業員1人が1時間あたりに生み出す利益を表す指標
人時生産性とは、従業員1人が1時間あたりに生み出す粗利を定量的に示す指標です。インプット(労働力)に対してどれだけのアウトプット(利益)を生み出しているかを明らかにできるため、生産性の可視化に役立ちます。
また人時という単位を用いることで、1人1時間あたりの作業量に換算し、複数人・複数時間にわたる業務も統一して把握することが可能です。企業規模や業態に関係なく、社内や部門間で生産性の比較がしやすく、経営指標として幅広く活用されています。
人時売上高との違い
人時売上高は、従業員1人が1時間働いたときに生み出す売上額を示す指標で、人時生産性との大きな違いは、粗利ではなく売上で算出する点です。
例えば、材料費が高く利益率の低い業態では、売上が高くても人時生産性は低くなる可能性があります。そのため売上を重視するのか、利益を重視するのかで適切に使い分けることが求められるでしょう。
特に飲食業や小売業など、売上の回転が重要な業種では人時売上高が役立ちますが、利益改善や付加価値の可視化には人時生産性の方が実態をより的確に反映する指標になります。
労働生産性との違い
労働生産性は、労働投入量(人数または時間)に対して得られる成果(売上や付加価値)を示す広義の概念です。
労働生産性が企業全体を俯瞰するマクロ的な経営指標であるのに対し、人時生産性は現場での人員配置や業務効率化に直結する指標といえるでしょう。両者を併用することで、より多面的な経営判断が可能になります。
人時生産性が注目されるようになった背景
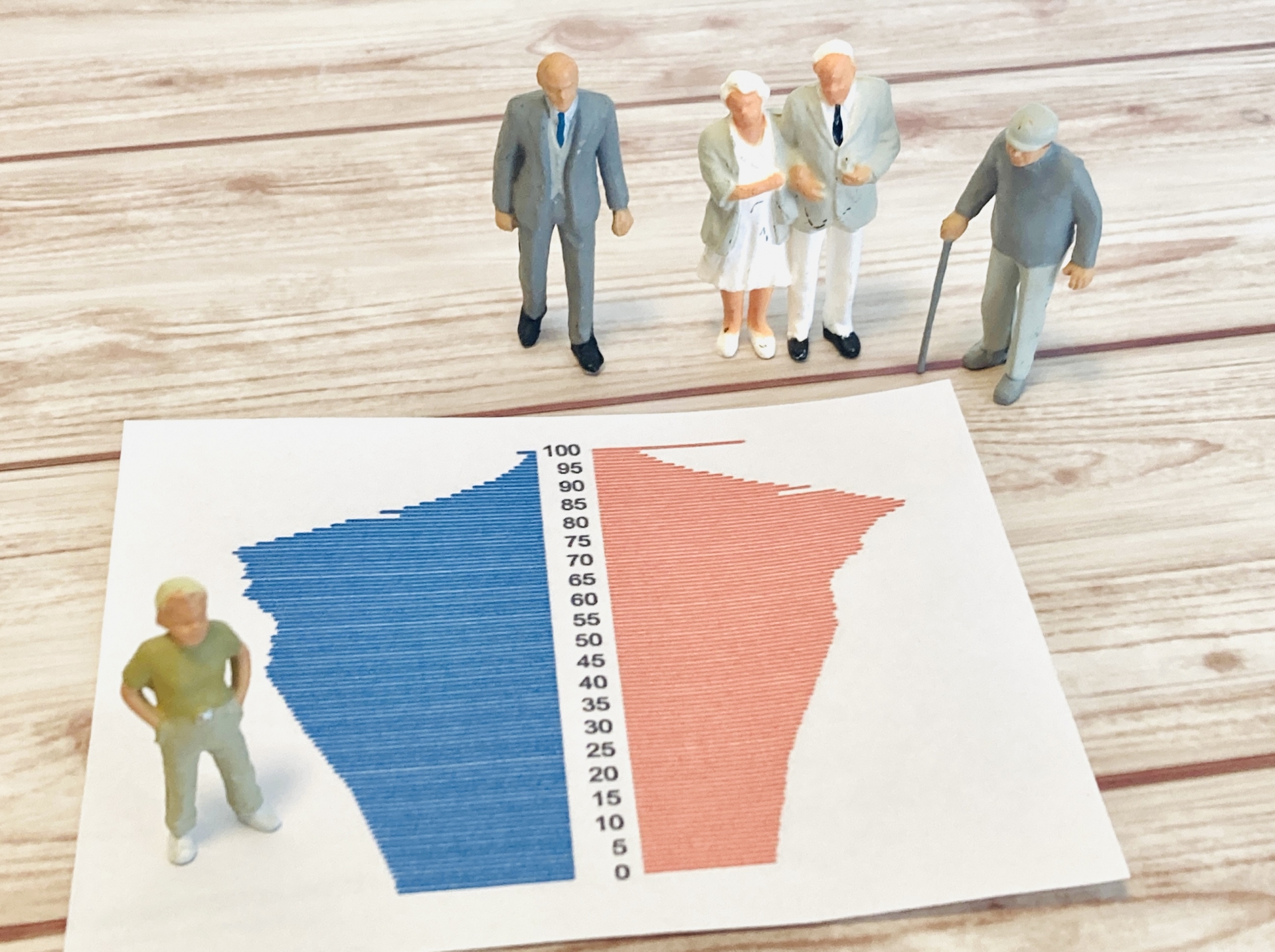
人時生産性が注目を集める背景には、少子高齢化による労働人口の減少や、働き方改革の推進といった社会的な変化があります。
限られた人員で成果を出す必要がある中で、従来の「1人あたり」の指標では実態を把握しきれないケースが増えてきました。また、派遣社員や時短勤務者の増加により、正確なパフォーマンスを測るには「時間あたり」の視点が重要になっています。
残業削減や業務効率化への圧力が強まる現在、人時生産性は定量的に生産性を可視化できる指標として、経営判断や改善活動の指針として不可欠な存在です。
人時生産性の算出方法と具体例

人時生産性を高めるには、まず現状の数値を正しく把握することが必要です。ここでは人時生産性の基本的な計算式と、実際の数値を用いた具体例をみていきましょう。
人時生産性の計算式
人時生産性は「粗利 ÷ 総労働時間」で算出します。ここでの粗利とは、売上高から売上原価(仕入れ・製造・人件費など)を差し引いた利益のことです。総労働時間は、該当業務にかかった「人数×作業時間」で計算します。
| 指標 | 計算式 |
|---|---|
| 粗利 | 売上高-売上原価 |
| 総労働時間 | 従業員数×労働時間 |
| 人時生産性 | 粗利÷総労働時間 |
人時生産性の具体的な計算例
次の計算例は、売上高や原価の調整により粗利は同額ながら、労働時間の違いにより人時生産性に差が出ている例です。
| 項目 | A社 | B社 |
|---|---|---|
| 売上高 | 1,200万円 | 1,400万円 |
| 売上原価 | 300万円 | 500万円 |
| 粗利 | 900万円 | 900万円 |
| 労働時間 | 3,600時間 | 4,200時間 |
| 人時生産性 | 2,500円 | 2,143円 |
見かけの売上に惑わされず、生産効率を基準に判断する視点が重要です。
人時生産性の向上を妨げる原因

人時生産性を高めるには、現場に潜むボトルネックを見つけ出すことが重要です。無駄な作業や非効率な体制が放置されていると、生産性は伸び悩んでしまいます。ここでは、人時生産性の向上を妨げる4つの主な原因を紹介します。
非効率な業務プロセスがムダを生み出す
業務フローにムダや重複があると、生産性はどうしても低下します。例えば、業務の流れが複雑すぎたり、同じ情報を複数の部署で何度も入力していたりするケースは、時間と労力の浪費につながるでしょう。
こうした問題を放置し続けると、短期的な対応では改善が難しく、慢性的なロスが積み重なっていきます。
人員配置のアンバランスが編成ロスを招く
必要な人員が足りない、あるいは過剰な状況が続くと、業務の効率は上がりません。例えば、ピーク時に人手不足となっている一方で、閑散時間帯は人が余っている状態は、典型的な編成ロスのパターンです。適切なシフト管理や役割分担が求められます。
アナログ作業が自動化を妨げている
紙での伝票処理やExcelによる手作業での集計など、アナログな運用が続いている工程は生産性を大きく下げる要因です。とくに定型的なルーティン業務では、手作業によるミスや確認作業が発生しやすく、時間のロスも避けられません。
コミュニケーション不足による判断の遅れ
現場での情報共有が不十分だと、確認作業や差し戻しが頻繁に起こり、業務がスムーズに進まなくなります。とくに複数の部門が関わる業務やリモートワーク環境では、指示の曖昧さや役割の認識違いによって、作業のやり直しが発生してしまうこともあるでしょう。
人時生産性を上げるには?実践すべき5つのポイント

人時生産性を向上させるには、全体の労働時間を減らすだけではなく、「どこに・誰が・どのように働くか」を見直すことが欠かせません。
業務プロセスや人材配置の改善、ITの活用など、具体的な施策を講じることで、持続的な生産性向上が可能になります。
1.業種別・部門別にデータを分析する
人時生産性の改善は、自社の課題を正しく把握することから始まります。業種別の平均値と比較することで、自社の水準を客観的に評価できるでしょう。
例えば、製造業の平均が2,837円、飲食業が1,902円など、業態ごとに特性が異なるため、適正値の把握や目標設定にも役立ちます。
さらに社内分析では、部門ごとの人時生産性を算出することで、改善が必要な部署や高パフォーマンスなチームを特定できます。全社一律の施策ではなく、部門ごとの最適化を進めましょう。
2.人員配置を見直し、適材適所で業務を効率化する
人時生産性を高めるには、業務内容に対して適した人材を配置することがポイントです。同じ業務でも、習熟度やスキルの違いでかかる時間は大きく変わります。
短時間で高い成果を出せる人材に業務を任せれば、総労働時間の削減が可能です。ただし、短期的な数値改善だけを目的とせず、教育・育成やチーム全体のバランスにも目を配ることが持続的な改善につながります。
3.業務プロセスの最適化でムダを排除する
業務フローを見直し、非効率な手順やボトルネックを取り除くことが、人時生産性向上の近道になります。
例えば、重複作業や過剰な確認工程などは、簡素化するだけで大幅な工数削減につながります。まずは現場の業務を可視化し、どの作業がムダになっているのかを特定。その上で改善を段階的に実施していきましょう。
4.ITツールやシステムを導入して単純作業を自動化する
繰り返し発生する単純作業は、ITツールでの自動化が効果的です。勤怠管理や在庫集計、レポート作成などは、人的ミスを減らすだけではなく、従業員を付加価値の高い業務へシフトさせることにもつながります。
自動化を進める際は、業務ごとに何が自動化できるかを見極めることが重要。効果の出やすい領域から段階的に導入することで、スムーズに定着しやすくなります。
5.正確な数値管理で改善の軸を明確にする
人時生産性は「粗利 ÷ 総労働時間」で算出されます。どちらの数値も正しく管理できなければ、分析結果に基づいた改善策も誤った方向へ進んでしまう可能性があります。
特に労働時間については、タイムカードや勤怠システムの入力ミスに注意が必要です。正確な数値を把握するためにも、ITシステムの導入や運用ルールの徹底が求められます。
人時生産性の可視化と改善で、自社のパフォーマンスを最大化しよう

人時生産性は、業務効率と利益性を数値で把握できる重要な経営指標です。意味や計算方法、改善ポイントを正しく理解することで、自社の課題を的確に捉え、生産性向上に向けた戦略を立てられます。
部門ごとの分析やIT活用を通じて、組織全体のパフォーマンスを最大化していきましょう。